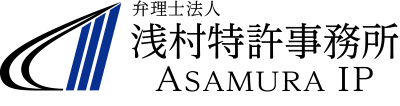2025年 7月25日
弁理士法人 浅村特許事務所
中国 スポーツシューズの意匠に関する無効審判

浅村特許事務所
中国弁護士 鄭 欣佳
意匠権と商標権とが抵触する場合、商標権侵害の判断基準を示す案件です。
スポーツシューズの意匠に関する無効審判
今回ご紹介するのは、意匠権と商標権が抵触した案件です。 先行商標の権利者は、スポーツシューズの意匠の一部が自社の商標と類似し、自社の商標権が侵害されたとして、無効審判を請求しました。
スポーツシューズのデザインには図形商標が含まれる場合が多く、意匠権と商標権の権利抵触が頻繁に生じます。本件の請求人はプーマヨーロッパ社「PUMA SE」(以下、「請求人」という)であり、意匠権者は「中乔体育股份有限公司」(以下、「意匠権者」という)です。両社ともにスポーツ用品の大手企業です。
本件の争点は、意匠の係争デザインが商標における判断基準である自社商品と他社商品と区別するための使用かどうかということです。この判断には、図形の類似性、係争デザインの役割、先行商標の知名度と識別力、意匠権者の意図、コラボ商標の使用など複数の側面を考えなければならないことを示しました。
その結果、国家知識産権局は請求人の請求を退け、意匠(以下、「本件意匠」という)の登録を維持しました。
本件審決は、意匠権と商標権とが抵触する場合の権利侵害の判断基準を示したものです。
1.本件意匠・係争デザイン及び先行商標


(本件意匠の立体図・左側面図) (本件意匠の右側面図)
 (先行商標1)
(先行商標1)
上記は本件意匠の関連図面及び1個の先行商標です。
請求人は7つの先行商標を挙げて、権利の抵触を主張していました。そのうちの1つが上記の先行商標1です。その他の先行商標は、先行商標1と類似しています。
上記枠内のデザイン(陸上トラックデザイン)が、係争デザインとなります。
2.請求人(プーマヨーロッパ)の主張
請求人の主張は以下となります。
① 本件意匠の右側面図は手前から奥へと無限に延びる陸上トラックデザインの形状を呈しており、先行商標のデザイン、構図などと類似している。一般的に靴類商品の側面図形は消費者の注目を集めやすく、その箇所に商標を配置しがちであるため、先行商標と酷似する係争デザインは公衆に混同を生じさせるおそれを生ずる。
② 先行商標は、請求人の著名商標である陸上トラックデザインと組み合わせて使用されることが多く、著名性及び識別力を有している。本件意匠は、意図的に先行商標の共通部分(陸上トラックデザイン)を模倣し、消費者にプーマ系の商標と認識させる可能性があり、有名なプーマブランドに便乗する意図があると考えられる。
③ 意匠権者の商標は、本件意匠の目立たない位置に配置されており、見落とされる可能性が高い。
④ たとえ意匠権者の商標が本件意匠に表示されていたとしても、コラボ商品である場合、2つの商標が同時に商品に表示されることも考えられるため、消費者は本件意匠に関わる靴はコラボ商品であると誤解する可能性も考えられる。
3.意匠権者(中乔体育股份有限公司)の反論
意匠権者は以下の反論を行いました。
① 本件意匠には、靴のかかと及び中敷きの目立つ位置に意匠権者の商標が表示されており、意匠権者は、自社商標を意図的に隠したり弱めたりしていない。
従って、意匠権者は自社と無関係の商標を使用する意図はないものと考えられる。

(本件意匠の平面図、枠内は意匠権者の商標)

(本件意匠の背面図、枠内は意匠権者の商標)
② 申立人は、デザインの一部を意図的に注目し、先行商標と比較している。係争デザインは靴のアッパーに施された補強デザインであり、踵を安定させ、足のぐらつきを防止するために使用されるものであって、商標としての機能は有しない。当該デザインは立体的に包み込むようなデザインであり、申立人が有する陸上トラックデザインではなく、従って誤認を生じさせるものではない。
③ コラボ商標の使用に関しては事前の許諾を必要とし、コラボ商標は通常、目立つ箇所に配置され正しく使用される。意匠権者の商標は中国で高い知名度を有しており、他者の商標に便乗する必要はない。また、意匠権者は請求人と直接の競業関係にあるため、意匠権者が請求人の商標を意匠権者の会社の商品に使用し、請求人のブランド名であるプーマの宣伝に協力する必要はない。
双方当事者の主張を総合的に考えると、本件の争点は、係争デザインに関連する公衆に対し、本件意匠に関わる商品の出所が請求人に由来する、またはこれと商業的な提携関係にあると誤認させるおそれがあるか否かにある、と認められます。
スポーツシューズのデザインは、商標として使用することができ、装飾模様として使用することもできます。装飾模様として使用される場合、必ず商標の役割を果たしているわけではありません。そのため、混同を生ずるおそれがあるかどうかについて判断をしなければなりません。
まずは、図形自体が類似するかどうかにより判断を行います。
係争デザインに係る図形は、踵部分の立体的な囲み構造であって、踵の一側面の靴底の上端から始まり、上方に向かって湾曲しながら延伸して踵部後端の上部に至り、さらに下方に湾曲しながら延伸して踵部の他方側面に位置する靴底上端部に至る構成を有し、全体としては中間部が狭く両端部が広い、斜めに配された馬蹄状の形状に近似する立体的な囲み構造です。
当該囲み構造の外周輪郭は滑らかな曲線により形成されており、その内部には扁平な楕円状および短線状の凹部が複数設けられています。
これらの凹部は、外周輪郭の形状に応じて、その幅および方向が変化します。
先行商標は平面図形であり、例えば先行商標1においては、図形は左下から右上に向かって湾曲しながら延伸し、次第に細くなる形状を有しています。その内部には、長手方向に沿って延びる2本の破線が描かれており、全体としては遠近感のある陸上トラックのような形状を呈しています。
これに対して、本件意匠は半包囲状の立体図形であり、先行商標と構図においても全体外観においても大きく異にします。両者の図形は類似するものではなく、外観に明確な差異があるため、誤認混同を生じるおそれはないと判断することができます。
次に、従来の商標権の事案とは異なり、本件の係争デザインは、靴の踵部における立体的な囲みデザインの一部に該当します。請求人は、当該部分が連続した図形であることを認めつつも、係争デザインの右側面図に示された部分のみを取り出して先行商標と比較すべきであると主張しています。これは、係争デザインが本件意匠の右側面図において示される踵部に使用されていることにより、商品の出所表示としての機能を果たしているとの主張に基づくものと理解できます。
したがって、本件における混同のおそれの有無を判断するにあたって、係争デザインの使用態様が実際に商品の出所識別機能を有しているか否かについても、併せて判断しなければなりません。
詳しく説明すると、
① 本件意匠は、白色の靴底、黒色のアッパー、さらに灰色、黄色、青色、赤色の図形および線条によって構成されており、アッパー部分における各色の図形や線条は前後で呼応し合い、全体として多彩なストライプ調のデザインを呈している。係争デザインは、踵部における当該全体図案の一部として構成されており、当該部分のみが強調された使用態様とはなっていない。
また、本件意匠においては、中敷きおよび踵部において、意匠権者自身が保有する図形商標が顕著に使用されており、とりわけ踵部の商標表示は争点デザインの直下かつ近接する位置に配置されている。踵部はスポーツシューズにおいて商標が最も一般的に表示される箇所の一つであり、意匠権者の自社商標はスポーツシューズ分野において相応の知名度を有していることから、関連する公衆は、当該顕著に表示された商標を通じて本件意匠の製品の出所を容易に識別することが可能である。
したがって、争点デザインは、商品の出所識別機能を果たすものとは評価できず、出所を表示する使用には該当しない。
② 請求人は、コラボ商品の主張に基づき、本件意匠において意匠権者の自社商標が使用されていることは、係争デザインがPUMAの商標と誤認される可能性を否定することができない旨、主張している。
しかしながら、コラボ商標の使用慣行に照らすと、正式なコラボ商品においては通常、正確な商標表示がなされ、広告宣伝等においても当該コラボ商標の所有者が明確に示されるのが一般的である。
本件係争デザインは、その全体または請求人が主張する一部分のいずれを見ても、先行商標とは明確に異なるものであり、当該デザインと意匠権者の自社商標がアッパー上で共存していることは、通常のコラボ商標の使用態様には該当しない。
請求人は、意匠権者が自社商標を使用し、請求人のブランドに便乗しようとする意図があると主張するが、意匠権者が実際にコラボの宣伝を行い、これにより公衆に誤認・混同を生じさせたとする証拠は一切提出されていない。
したがって、係争デザインと意匠権者の自社商標がアッパー上に共存していることのみをもって、関連する公衆がコラボ商品であると誤認するとは考え難く、混同のおそれは認められない。
③ 請求人が主張する先行商標の知名度および顕著性に関しては、以下の判断が下された。
本件の当事者双方は、いずれも相応の知名度を有する企業であり、かつ同一カテゴリーの商品を取り扱う競業関係にある。
そのため、本件は、無名の事業者が周知ブランドの信用に便乗するような事案には該当しない。
請求人が主張する顕著性は、7つの先行商標に共通する陸上トラックデザインの図形にあるとしているが、この図形が識別力を獲得したのは、主に請求人の著名商標と長年にわたり組み合わせて使用され、かつ一定の位置(例えばシューズの内側面・外側面等)に継続的に表示され、段階的に蓄積・強化された結果である。
先行商標のこれまでの使用実績に照らせば、その顕著性、すなわち出所表示機能の強さは、当該図形の使用位置と密接に関連しているといえる。
これに対し、係争デザインは踵部に立体的に囲まれた箇所にあり、先行商標が通常配置されるシューズの内側または外側とは異なる使用態様となっている。加えて、係争デザインが配置された付近には、意匠権者の自社商標が表示されており、当該商標もまた相応の知名度を有している。
よって、両者の図形は形状において明確に異なっており、配置や使用方法にも顕著な差異があることから、需要者が係争デザインをもって請求人の商品であると誤認・混同するおそれはないと考えられる。
総合的に考えると、係争デザインは、本件意匠の構成要素の一部として用いられているに過ぎず、目立つ態様で使用されておらず、出所表示としての顕著な識別力を有しているとは認められません。 また、当該デザインの下部には、意匠権者自身の著名な商標が明確かつ顕著に表示されており、商品の出所を適切に表示し得る状況にあります。
意匠権者による係争デザインの使用態様には、他人の商標に便乗する意図が明白に認められるものではなく、自社商標の使用方法も業界の通常の取引慣行に則ったものです。
さらに、係争デザインの外形が右側面図において、先行商標の対応する線形と一定程度の類似性を有しているとしても、これにより関連する公衆が商品の出所について誤認・混同を生じさせるおそれは低いものと考えられます。
ましてや、本件意匠の出所が関連する公衆により十分に識別され得る状況においては、請求人との間に何らかの関係が存在するとの誤認を生じさせることはないと判断されます。
従来、意匠権と商標権との抵触に関する案件においては、係争意匠において顕著に使用されている標識と、先行商標との対比を直接的に行うことが多く、判断のポイントは図形の類否に集中していました。
しかし、図形の類似性に関する判断は、混同の可能性を判断には重要な要素ではあるものの、唯一の判断基準ではありません。
複雑な事案においては、混同の可能性に影響を与えるその他の要素も総合的に考慮する必要があります。
例えば本件においては、単に図形の類似性を判断するだけでなく、係争デザインの使用態様、当該業界における取引慣行、さらには消費者の認識といった複数の要素を総合的に勘案して、審査結論が導き出すことが求められます。