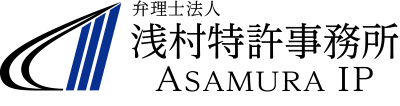2024年 7月 5日
浅村特許事務所
中国 ネオジム焼結磁石の特許ライセンスに関する独禁法判例

浅村特許事務所
中国弁護士 鄭 欣佳
中国の磁石メーカー4社と日立金属株式会社(現「株式会社プロテリアル」)との間、ネオジム焼結磁石の特許ライセンスをめぐって、独禁法違反の訴訟が行われました。
中国最高人民法院で行われた上訴審において、日立金属株式会社の逆転勝訴の経緯を紹介します。
ネオジム焼結磁石の特許ライセンスに関する独禁法判例
2014年12月、中国の磁石メーカー4社①が日立金属株式会社(2023年 1月からの新商号は「株式会社プロテリアル」です。以下「日立金属」といいます。)を相手に、ネオジム焼結磁石特許のライセンスを当該4社(以下「原告4社」といいます。)に与えないことが、市場支配的地位の濫用にあたるとして、中国寧波市中級人民法院に訴訟を提起しました。
2021年 4月、市場支配的地位の濫用を認定した一審判決(以下「一審判決」といいます。)が下されました。
日立金属はその判決を不服として、中国最高人民法院に上訴しました。
中国最高人民法院は2023年12月、一審判決を取り消し、原告4社の訴訟請求を棄却する二審判決(以下「二審判決」といいます。)を下し、日立金属の勝訴となりました。
今回はその逆転勝訴の経緯を紹介させていただきます。
1.争点
中国国務院独占禁止委員会が制定した「知的財産分野に関する独占禁止の指南」によると、知的財産権に関わる市場支配的地位の濫用の判断には、独占禁止法第3章の規定が適用されます。
通常、まず関連市場を画定し、事業者が関連市場において支配的地位を有するか否かを判断します。
そして、各事案の状況に応じて、当該行為が知的財産権の濫用、競争を排除または制限するものに該当するか否かを分析します。
この考え方により、二審判決は一審判決と同じように、争点を以下の4つに絞りました:
(1)関連市場の画定
(2)市場支配的地位を有するかどうかの判断
(3)支配的地位を濫用したかどうかの判断
(4)損害賠償
2.関連市場を画定する基準
2007年中国独占禁止法②(以下「独禁法」といいます。)の12条において、「関連市場」とは、事業者が一定の期間内に特定の商品またはサービス(以下、「商品」と総称する)で競争を実施する商品の範囲と地域の範囲を指します。
従って、「関連市場」を画定する際に、①期間、②商品、③地域について考えなければなりません。
すなわち、国務院独占禁止委員会が制定した「関連市場の画定に関する指南」により、独占禁止の実務において、通常、関連する商品市場及び関連する地域市場を画定しなければなりません。「関連する商品市場」とは、商品の特性、用途、価格などの要因に基づき、需要者が比較的密接な代替関係を有すると認識する同グループまたは同種類の商品で構成される市場のことを指します。
「関連する地域市場」とは、需要者がより緊密な代替関係を持つ商品を入手する地理的地域を指します。
「関連市場」の画定は、通常、商品の特性、用途、価格、その他の要因に基づいて行うことができます。必要であれば、供給の代替分析を行うこともできます。
3.関連市場の画定についての二審判決の判断
1.期間について
2014年3月、原告4社を含め7社の連盟は、日立金属に対し、オジム焼結磁石特許のライセンスについて交渉するため、アメリカの弁護士に依頼しました。交渉のきっかけは、2013年 7月、日立金属が公表した新しいライセンスリストの存在です。そのリストは一審判決が出るときまで内容が変わりませんでした。
本件にかかわる関連市場はライセンスの拒否に基づいた技術市場であるため、関連市場の期間は2013年 7月から一審の法廷弁論終了日と判断されました。それは一審判決の判断と同様でした。
2.関連する商品市場について
一審判決は、関連する商品市場は「ネオジム焼結磁石必要特許③市場」であるという結論を下しましたが、二審判決はその結論を覆しました。その理由は以下となります。
まず、両当事者の主張・提出した証拠には矛盾があったということです。
原告4社は、日立金属の関連特許がネオジム焼結磁石の製造に必要不可欠な特許、重要な特許だと主張しつつ、自社の製造したネオジム焼結磁石は日立金属の特許権を侵害していないと主張しました。
日立金属は中国国内においてライセンスした8社以外の約200社のネオジム焼結磁石のメーカーに対しても、今回の裁判まで権利侵害訴訟を提起したことはありませんでした。
次に、ネオジム焼結磁石の原料及び製造技術からすると、日立金属のネオジム焼結磁石特許は必要特許であるという主張を証明できる証拠が不足していました。ネオジム焼結磁石の製造業界において、その構成成分が基本的に確定されていて、公知技術となっていましたが、各メーカーの製造したネオジム焼結磁石の構成成分は多少異なりました。その相違は、メーカー各自が有する特許、営業秘密、または公知技術に基づいています。
日立金属が有するネオジム焼結磁石成分に関する特許は1982年から1983年の間に出願し、登録され、本件の一審裁判が提起された2014年までには既に30年が経っており、公知技術となっています。
原告4社が技術専門家のレポートを援用し、日立金属の特許パッゲージを避けようとすると生産コストが大幅に増える特許があると主張しましたが、説得力がある理由や証拠は提出できませんでした日立金属側の技術専門家は、その主張を否定しました。
さらに、日立金属は全世界において600件以上のネオジム焼結磁石に関する特許を有していました。その地域はアメリカ、ユーロッバ、及び中国にも及んでいました。中国において、日立金属は90件の関連特許を有し、8社にのみライセンスを供与していませんでした。その8社は日本を除き、全世界においてネオジム焼結磁石の製造・販売をすることができます。
しかし、日立金属のライセンスを受けてない中国のネオジム焼結磁石メーカーは、中国国内において製品を製造し、ユーロッバなどアメリカ、日本以外の国に輸出する際に、日立金属に権利行使されたことがありませんでした。原告4社は、あるレポートを援用し、ネオジム焼結磁石特許のライセンスを受けていない企業が特許を受けた企業に10%の代理手数料を支払わなければならず、特許を受けた企業の名義で輸出をしなければならない旨を主張しました。
しかし原告4社は、代理手数料を支払った事実を証明できる証拠を提出することができず、日立金属側も代理手数料の存在を知らず、ライセンス契約にはサブライセンスを禁止する条項が入っていることを主張しました。そのため、代理手数料を支払ったという証拠を有していません。
従って、原告4社が主張した「日立金属のライセンスを受けていない中国ネオジム焼結磁石企業の製品はアメリカなどの指定国に輸出できない」ことを証明できる証拠が充足せず、事実に対する誤判またはトレンドに対する誤解があったと考えられます。
本件においては、関連市場を画定するため、客観的、信憑性があるデータを用いて、経済学の分析方法により判断をしなければなりませんでした。
しかし、両当事者も本件の関連市場を画定するだけの信憑性があるデータを提出することができず、提出した証拠では各自の主張を裏付けることができませんでした。 立証責任を考えると、原告4社が日立金属の関連特許は必要特許であることを証明すべき責任を負うため、該証明ができなければ、原告4社に不利な結果となり得ます。
ネオジム焼結磁石の需要の代替性等を考えると、本件の関連する商品市場は、ネオジム焼結磁石の製造技術市場、緊密な代替関係を有する特許技術及び非特許技術が含まれています。関連する技術市場に複数の競争関係を有する技術が存在する場合、当該技術を実施する下流商品の市場シェアにつき、さらに正確に関連する技術の市場の状況を示すことができます。
従って、関連市場の技術所有者の市場に対する影響力は、ネオジム焼結磁石市場の市場シェアによって確定することができます。
3.地域について
ネオジム焼結磁石は既に全世界において製造されており、関連する地域は全世界だと判断されました。
その結論は一審判決の結論と変わりありません。
4.日立金属は市場支配的地位を有するかどうかの判断
独禁法第17条第2項には、「本法に言う市場支配的地位とは、事業者が関連市場において商品価格、数量、またはその他取引条件を規制することができる、又はその他事業者が関連市場へ参入することを妨害できる、若しくは影響を及ぼす能力を備える市場の地位を指す。」との規定があります。
従って、ある事業者が市場支配的地位を有するといえるのは、関連市場において取引条件を規定できるか、若しくは、他事業者が関連市場へ参入することが妨害できるか、の何れかである場合となります。
独禁法第18条には、市場支配的地位を有するかどうかの判断を左右する下記の要素が規定されています。
① 関連市場の取引相手が代替技術や代替製品に切り替える可能性とそのコスト
② 知的財産権を用いて供給される商品に対して下流市場の依存度
③ 取引相手が事業者に対する牽制力 等
事業者が知的財産権を有することは、市場支配的地位を有することを判断する要素の一つですが、知的財産権を有することだけでは、その事業者が関連市場において市場支配的地位を有すると推定することはできません。
原告4社の提出した証拠から、二審判決は一審判決の「日立金属が市場支配的地位を有する」とする結論を変更し、「日立金属が市場支配的地位を有しない」という結論を下しました。その理由は以下の通りです。
まず、日立金属及びそのライセンス企業が占める市場シェアは高くないということです。日立金属が提出したレポートによると、日立金属及びそのライセンス企業が占めた中国国内の市場シェアは20%以下であり、海外の市場シェアはさらに低くなっています。
次に、その提出された証拠では、日立金属の特許は技術上代替できないことを証明することはできず、逆に、その特許は技術上代替できることを証明しました。なぜなら、1983年に登録されたネオジム磁石化合物の特許権の存続期限が満了してしまい、1997年に登録されたもう一つの成分特許権の存続期間も2014年において満了しました。成分に関する特許、特に最初のネオジム磁石化合物の特許権の存続期間が満了してから、市場に特許権を侵害しない技術が出ていると考えられます。
また、原告4社が提出したある上場企業の法律意見書によると、その会社は日立金属の技術を使用していないのに、日立金属に「ライセンス費用」の支払いを行っていました。
この法律意見書から、日立金属からライセンスを受けている企業であっても、実際にその技術を使用していない可能性があることを明らかにしました。その上、原告4社も自社が製造したネオジム焼結磁石は日立金属の技術を使用していないことを主張しています。
従って、ほかに代替的な技術がある場合、通常、その技術の所有者が、他の事業者の市場参入に影響を与えたり、取引条件をコントロールしたりする市場支配力を持っていると直接的に認定することは難しいといえます。
続いて、日立金属の特許はビジネス上代替できない、という主張は認められないということです。2014年から2017年の間、原告4社のネオジム焼結磁石の生産量及び売上が逐年増加していることからも、日立金属からライセンスを受けていないことによって、市場参入ができないということはありませんでした。
また、中国のネオジム焼結磁石の生産量も2014年から大幅に増加していました。日立金属からライセンスを受ける企業が増加していないにも拘わらず、ネオジム焼結磁石の総生産量が増加していることから、日立金属が技術市場においても、また、原材料市場においても、市場支配的地位を有しないということが証明されました。
5.不可欠施設法理の適用
二審判決は、日立金属が市場支配的地位を有しないという結論により、支配的地位の濫用及び損害賠償の判断を見送り、原告4社の請求を棄却しました。
一審判決は、不可欠施設の法理により、日立金属の特許が不可欠施設となっていると判断しました。
その理由は、
① 日立金属の特許が競争を行う上に必要不可欠な施設になっている
② 日立金属が特許権者としてその施設を支配している
③ 競争する事業者が合理的な範囲でその施設を複製するのは不可能である
④ 原告が明確にライセンスを求め、相応の対価を支払う意思を表明したにもかかわらず、日立金属は競合他社が
その施設を利用することを拒否していた
⑤ 日立金属がその施設のライセンスを提供するのは可能である
⑥ 施設の利用拒否には正当な理由がない であるとしています。
二審判決は不可欠施設の法理の適用を評価しませんでしたが、日立金属の関連特許は回避不可能ではなく、日立金属は関連市場において支配的な地位を有していないと認定し、実質一審判決の不可欠施設の認定を覆しました。
2023年に公表された「競争を排除または制限するための知的財産権の濫用の禁止に関する規定」では、2015版の同規定に記載した不可欠施設に関する条文を削除し、不可欠施設の適用について、慎重な姿勢を見せました。
6.関連する商品市場の判断
日立金属が市場支配的地位を有するかどうかを判断する際に、一審判決はネオジム焼結磁石必要特許市場を関連する商品市場にし、その市場において、代替的な技術がなく、もしくは代替的な技術を使用する場合にそのコストが高い等の理由で、日立金属が市場支配的地位を有すると判断しました。
二審判決では、提出された証拠が日立金属の技術が代替できないことを証明できない場合、関連する商品市場をネオジム焼結磁石の製造技術市場としました。技術市場に複数の競争関係がある技術が存在する場合、下流商品の市場シェアはもっと正確に関連する技術の市場の状況を示すという考え方を明らかにしました。
結果、日立金属及びその技術ライセンスを受けた企業のネオジム焼結磁石の市場シェアは低いため、市場支配的地位を有しないと判断されました。
ここで、最高人民法院は、特許権者の市場支配的地位の有無を判断する際に、まず代替的な技術の有無を確認し、技術市場と下流の商品市場の関係を把握し、結論を下す考え方を示しました。
本件において、中国最高人民法院が非標準必須特許の特許権者の契約自由を尊重し、強制ライセンスに対して慎重な考えを示しました。 外国の特許権者が中国に進出する際の安心材料となるではないかと思います。
注:
① 寧波科田磁業有限公司、寧波永久磁業有限公司、寧波同創強磁材料有限公司及び寧波華輝磁業有限公司の4社です。
② 本件には2007年の「独占禁止法」が適用されます。
③ 日立金属の特許は標準必須特許ではないため、「必要特許」という呼び方にしました。